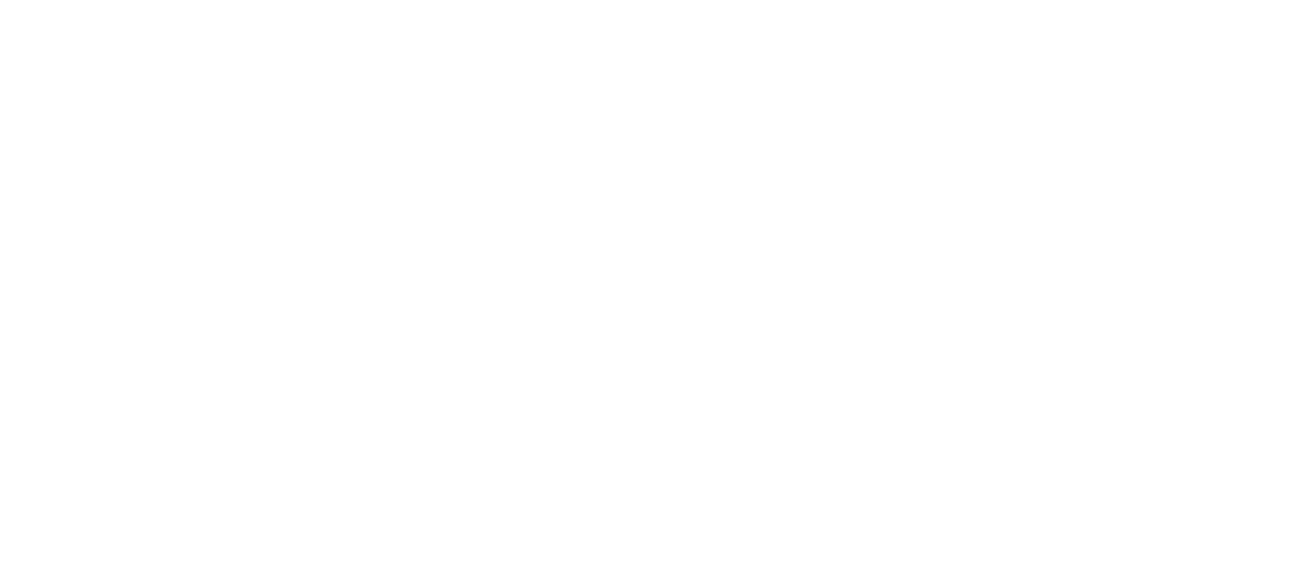REPORT
刊行物・研究報告

その他刊行物
令和3年度(2021年度)

REPORT
EVENT
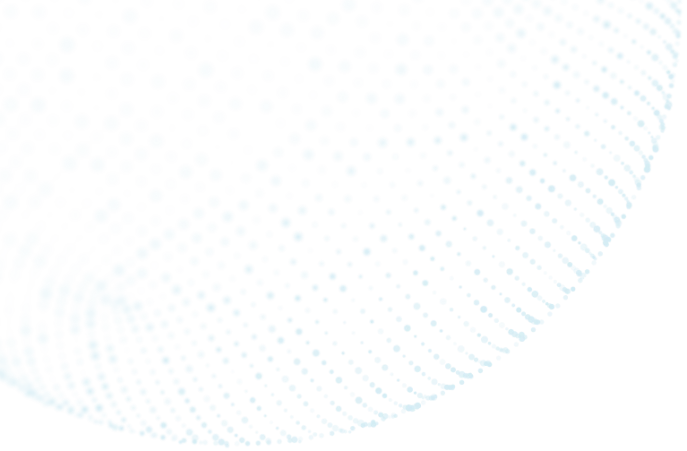
SUPPORT
(公財)福岡アジア都市研究所では研究所の活動趣旨に賛同していただける方に賛助会員としてご加入いただいています。
ぜひご入会をご検討ください。
特典 1
研究所主催のセミナー等の
開催情報を優先的に
ご案内します
特典 2
研究紀要「都市政策研究」や
総合研究報告書などを
無料でお届けします
特典 3
URCの資源を活用して
研究活動ができます
(会員研究員制度)
特典 4
ホームページで会員名
(希望する法人会員のみ)を
ご紹介します